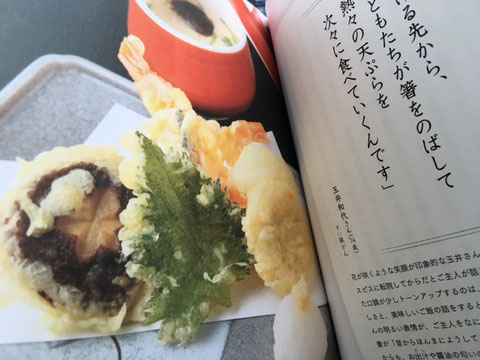「余命がわずか3週間だとすれば、あなたなら何を食べますか?」これまであらゆる場面で使い古されてきた、ありきたりで陳腐な質問ですが、それが実際のホスピスにおいて末期のがん患者さん14名に聞いた、最後に選ぶリクエスト食となると話は違います。最後に選ぶ食事には、その人の生きた証が詰まっているのです。食べることは生きることであり、たとえ食べられなくなったとしても、食べようとすることで人は生きることができる。著者が最後に記している、「『死』が近づいてきているとしても、生きている限り、人はやっぱり死から遠ざかっている」という言葉には、死にゆく人たちと向き合ってきた実感が込められています。彼ら彼女らが語るエピソードに添えられたリクエスト食の写真を見るだけで、どれも美味しそうで、不思議と生きる力が湧いてくるようです。
本書の中で紹介されているのは、淀川キリスト教病院ホスピス・こどもホスピスにおいて、緩和ケアの一環として実施されているリクエスト食という取り組みです。病院によって決められるのではなく、患者さんひとり一人が自分で決めてリクエストする献立。ただ美味しいものを食べたいということだけではなく、自分の人生においてのご馳走を食べるということです。末期のがん患者さんたちにとっては、自分が今日選ぶ食事がまさに最後のそれになってしまうかもしれません。そんな中で選ぶ最後のリクエスト食からは、その人の歩んできた人生の日々の風景や思い出、エピソードが溢れて出てきます。食事と生きてきた記憶というのは、実に密接に結びついているのです。
冒頭の質問を自らにしてみたとき、すぐに思いつく答えはありませんでした。ご馳走とは無縁の貧しい生活をしてきたわけではなく、かといって、人前で語れるような美食家でもないからかもしれません。それでもゆっくりと思い出してみると、ひとつありました。
私が小さい頃に、両親に連れて行ってもらった、吉祥寺の葡萄屋というお店のステーキです。なぜそのお店に行くことになったのか覚えていませんが、薄暗い店内と料理人がテーブルの横でステーキを焼いてくれたことをはっきりと覚えています。そして、あのステーキの美味しさ。こんなにも美味しいお肉が世の中にあったんだ!と小学生ながらに感動したものです。もう遥か昔の話ですし、たった1度しか行ったことがないため、お店自体が今も存在するのかさえ分かりませんが、家族との良き思い出のひとつとして、私の胸に刻まれています。最後のリクエスト食としては、あのステーキをもう1度食べてみたいですね。
ひとり一人の人生と最後の食事は密接に結びついているものであり、それゆえに10人いれば10通りのリクエスト食があるのでしょう。栄養を摂取するためだけに食事はあるのではなく、食べることは生きることであり、日常の風景の大切なひとコマであり、私たちの人生を形づくっているものなのですね。そして今回、食べることについて改めて考えてみて、何を食べたのかだけではなく、誰とどこで食べたのかも大切なのだということがよく分かりました。これからもたくさんのご馳走の思い出をつくっていきたいと思います。あなたにとっての人生最後のご馳走はなんですか?